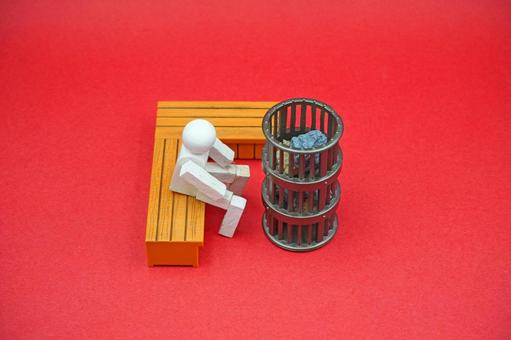大変なサウナブームです。温浴施設や大きなホテルはもとよりビジネスホテルでもサウナを備えた施設が多くなりました。根強い人気を維持する街中の銭湯でも、天然温泉やサウナをウリにするところも多くなりました。全国各地のサウナの紹介や、サウナの作法の指南本も街に溢れ、サウナから冷水風呂、その後は外気浴で「ととのう」サイクルなどは、周知のこととなっています。
ところでサウナの効用は、何なのでしょうか。まずは、大量の汗をかいて老廃物を排泄し、肌の新陳代謝を促進することでしょうか。また、温熱刺激で血管が拡張し、血行がよくなることも指摘されています。温熱により体が温まると痛みが和らぐことや、自律神経が調節されて免疫力が高まり、肺炎や感冒などの感染症を予防できるとも言われています。一方、サウナのデメリットとしては、大量の汗をかくので脱水症状を引き起こすリスクや、高温環境に長時間いることで熱中症になるリスク、冷水風呂での急な血圧の変動が高齢者や心血管系が弱い人へのリスクとなることが指摘されています。
結局、サウナは体にいいのでしょうか、それとも悪いのでしょうか?順天堂大学教授の自律神経の専門家である小林弘幸氏の説明が、シンプルで明快です。小林氏自身も以前は「サウナは熱くて苦しくて、体にいいはずがない」という意見でしたが、体験を通じてサウナファンになった経緯の持ち主です。
小林教授の考える「健康」の概念はシンプルで「血流がよい」ことです。血流が良ければ全身のすべての臓器や組織に好影響を与える根源的なケアとなるというのです。人間の身体には動脈と静脈、毛細血管という無数の血管が張り巡らされています。その血管を通り身体中に栄養を届け、老廃物を捨ててくれるのが血液で、その流れが血流です。また、血流は自律神経によりコントロールされています。自律神経とは私たちの意識とは無関係に働く神経のことで、主に血管に沿って全身に張りめぐらされ、脳と各臓器とをつないでいます。自律神経のバランスが崩れると、さまざまな不調が現れ、蓄積すると思わぬ大病に罹ることもあります。
サウナには、血流をよくするための血管と自律神経を鍛える絶大な効果があるのです。まず、血管はサウナの高温環境で拡張しますが、水風呂の低温環境で一気に収縮します。その後、外気浴や室温での休憩で再びゆるやかに拡張していきますので、血液がサーッとスムーズに流れ出します。人間は、血管が拡張して血流が促進されるときに「気持ちいい」という感覚を覚えるのです。次に、自律神経は高温環境や低温環境では交感神経が働き血圧が高く緊張した状態となりますが、逆にリラックスした環境では副交感神経が働き血圧が下がり体を休める態勢となります。サウナと冷水風呂の緊張状態と、その後の外気浴でのリラックスは、自律神経の振れ幅を強制的に大きし、バランスを整いやすくしているのです。この二つの効果により、私たちは「ととのったー」と感じるわけです。
湯舟に浸かる場合は、水風呂はあまり使いませんので自律神経に適度な刺激を与える「温度差」が生まれません。また、お風呂だと身体は温まりますが、水圧がかかるので血管はさほど拡張されません。つまり、サウナが血流を良くするにはもっとも適した方法となります。サウナ浴中は平常時と比べ、なんと約2倍の血液が全身に流れています。血管が広がり、大量の血液が全身に流れ、栄養と酸素を届けてくれていると想像しただけで、みるみる身体が健康になることがイメージできます。最後にサウナ浴での注意点ですが、健康的にサウナを楽しむためには自分の体から発せられる「気持ちいい」という感覚に素直に従い、無理をしないことが重要だそうです。最初は2~3分から始めても、身体を十分に冷やすことを繰り返すと、徐々に無理なく長い時間サウナに入れるようになってきます。
----------------
自律神経の専門家の順天堂大学小林弘幸教授のサウナに関する記事です。
サウナに関する別の記事があります。ご興味のある方はお立ち寄りください。